日本は高齢化社会と言われる中で、サービス介助士の需要は高まっています。本記事では、サービス介助士になるためにはどんなステップ・試験があるのかについて解説していきます!
Contents
サービス介助士とは?

サービス介助士とは、主にサービス業などの現場で、高齢者や障害のある人などサポートを必要としている人へ適切な手助け・介助・サポートする民間資格です。
サービス介助士は公益財団法人日本ケアフィット共育機構が発行する民間資格で、「ケアフィッター」とも呼ばれています。サポートが必要な人に対し、その場に合ったケアをする(=ケアにフィットする)人です。

サービス介助士は、車椅子で移動する方に対するサポート、身体を動かしにくい高齢者へのお手伝い、視覚・聴覚が不自由な方への手助けなど幅広い分野で活躍しています。
サービス介助士の資格は、2000年に「サービス介助士2級」という名称で広く知られるようになり、2015年から現在の「サービス介助士」に資格名が変更され、2021年6月1日時点で全国に約19万人が取得しています。
サービス介助士の活躍の場
日常生活をサポートするサービス介助士は、その資格の名前から介護施設のみでの活躍とお思われがちですが、実は公共交通機関やサービス業でも活躍しています。
交通公共機関の企業によっては、サービス介助士を取得してる駅員・スタッフにはオリジナルバッチをつけていたりします。是非お近くの駅で探してみてください。
サービス介助士は、適切な介助・サポートを淡々とこなしていくのではなく、「おもてなしの心」を重要視する資格です。
サービス業の仕事にも応用できる考え方であることから、サービス介助士の勉強を通して身についた知識や介助術は、介護の現場に限らず、ホテルや旅行会社、ボランティア施設など、様々な業種・場面で活用しています。
サービス介助士の資格難易度

サービス介助士の資格試験は、合格率が約8〜9割なので比較的受かりやすい資格と言えるでしょう。サービス介助士のテキストに目を通し、しっかりと勉強していけば問題なく合格できる資格です。
働きながら資格取得する方も多く、誰でもチャレンジしやすい環境となっています。
資格取得までの流れ
サービス介助士になるためには、まずは資格を運営している日本ケアフィット共育機構へ申し込みをすることが第一ステップとなります。
| 資格取得までの流れ | |
| ①申込 | 日本ケアフィット共育機構へ申込(後日テキスト・課題送付) |
| ②学習 | 日本ケアフィット共育機構から郵送されたテキストで自宅学習 |
| ③課題提出 | テキストと同封されていた課題を提出 ※課題100問、60点未満は再提出 ※申込から課題提出まで6ヶ月以内目標 |
| ④実技教習 | オンライン・対面での実技教習 ※オンライン講座(6~7時間)を受講&対面実技教習1日、 又は対面形式のみでの実技教習2日 |
| ⑤検定試験 | 筆記試験50問、70点以上合格 ※不合格の場合は再試験制度あり(有料) 申込から検定試験まで12ヶ月以内 |
日本ケアフィット共育機構から配布されるテキストは230ページほどとなり、かなり分厚いテキストとなっています。週一で勉強するのではなく、知識を身につけるためにも毎日コツコツと勉強することがカギです。
12ヶ月という猶予はありますが、期間が伸びれば伸びるほどモチベーションを保つのも難しくなります。ご自身の生活を見ながら短期集中で資格取得を目指しましょう!
ユーキャンに「准サービス介助士」の講座がありますが、こちらは「サービス介助士」へのステップアップの資格で、異なる資格のため注意しましょう。
また、産業能率大学で「サービス介助士受験基礎」という講座がありますが、こちらだけではサービス介助士の資格は取得できませんのでご注意ください。
詳しくは日本ケアフィット共育機構のQ&Aをご確認ください。
サービス介助士の実技内容

サービス介助士の課題合格後、必ず実技の実施があります。実技教習は2日間で座学・実践形式となっており、サービス介助士として現場に立った時、迷わずサポートができるような内容になっています。
座学では高齢化など社会を取り巻く現状で過ごしていくためにどのような心構えが必要なのかを学び、実践では高齢者疑似体験・車椅子利用者への接遇・視覚障がい者への接遇方法を実践形式で体験します。
サービス介助士の実技は堅苦しい雰囲気ではなく、実際に体を動かして行うため楽しみながら受講することができます。最初は緊張するかと思いますが、サービス介助士として働くために、受講の際は積極的に参加していきましょう。
実技の申込方法
サービス介助士の実技は日本ケアフィット共育機構のHPから予約することができます。受講方法には、オンラインと対面型の2通りがあります。
- オンライン講座+1日対面型実技教習コース
- 2日間対面型実技教習コース
どちらを選択しても試験の合否に変わりはないので、実技会場・日程を見ながらご自身の都合に合わせて申し込みましょう。
オンライン講座+1日対面型実技教習コース
オンライン講座はコロナ対策として2020年に設けられました。オンラインでの講座は6〜7時間あり、もう1日は対面型(9:30〜17:00)での実技となります。
対面型の日程は関東が月に10回以上、関西が月に5回以上開催しています。その他全国各地で行なっていますが、頻度が少なくなっているのでご注意ください。
2日間対面型実技教習コース
オンライン講座もありますが、インターネット環境がない方もいらっしゃるので、従来どおり2日間対面形式の教習もあります。2日間とも9:30〜17:00の5.5時間です。
こちらも全国各地で行なっていますが、オンライン講座コース同様、開催が少ない地域があります。
また、土日の2日間で行なっている日程もありますが、やはり人気枠なのですぐに定員に達する可能性があります。希望の日時がある際は早めに予約しましょう。
サービス介助士の試験内容
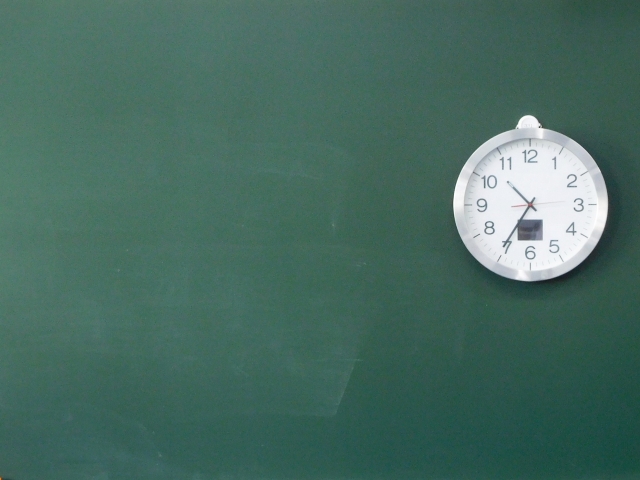
実技を終えたらいよいよ試験です。試験は実技教習後に実施されます。サービス介助士の試験はマークシート形式の3択問題で、1問2点の問題が50問出題され、100点満点で70点以上が合格となっています。
試験内容については公開されていませんが、日本ケアフィット共育機構のHPから模擬試験を体験することができます(※利用料金2,200円)。
本番はマークシートの筆記ですが、模擬試験はパソコンやスマートフォンで24時間いつでも好きな時間に受験可能です。即時に自動採点されるため、合否がすぐわかり、間違えた箇所も閲覧できるようになっています。
サービス介助士になるための費用

サービス介助士のテキスト・実技教習・検定試験までの費用は41,800円(税込)です(2022年12月現在)。市販のテキストだけで取れる資格に比べると高いように感じますが、学校や通信講座に比べると比較的出しやすい金額となっています。
日本ケアフィット共育機構のHPから申し込みを行い、自動返信メールに記載の銀行口座に振込み、もしくはクレジットカードでの支払いとなります。
またサービス介助士には3年毎に資格更新制度があり、更新料は1,650円(税込)となっています。
まとめ
- サービス介助士は、高齢者や障害のある人などサポートを必要としている人へ適切な手助け・介助・サポートする民間資格
- 介護施設はもちろん、公共交通機関やサービス業でも活躍している
- 合格率が約8〜9割なので比較的受かりやすい資格
- 最短で2ヶ月で取得可能
- 課題提出後の実技教習は2日間で座学・実践形式
- 試験はマークシート形式の3択問題(模擬試験可能)
- 費用は41,800円(税込)
サービス介助士は様々な場所で活躍しており、今後も需要が高まってくる資格です。社会人・学生だれでもサービス介助士を目指すことができます。
介護に携わりたい、人の役に立てる仕事がしたいと考えている方にぴったりの資格です。ぜひサービス介助士として働くために一歩踏み出してみてはいかがでしょうか。










