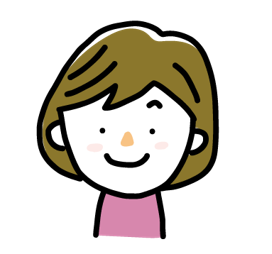このようにカルテを含む医療情報がほとんどの病院で電子化・IT化されていますよね。電子化することによって多種多様な機関と情報の共有と連携がしやすいのです。そのため電子カルテや医療情報システムの知識とスキルはとても重要なものになっています。
この記事では電子カルテオペレーション実務能力認定試験について以下のことを説明していきます。
- 電子カルテオペレーション実務能力認定試験について
- 試験の内容
- 資格取得までの流れ
- 試験の難易度や合格率
少しでも興味のある方はぜひ最後まで読んでいってください。
Contents
電子カルテオペレーション実務能力認定試験について

電子カルテオペレーション実務能力認定試験は全国医療福祉教育協会が実施する試験です。国家資格ではなく民間資格となっています。電子カルテとは電子化された診療録のことであり、医療機関の各種システムとの連携から成り立っているのです。
2017年の時点で電子カルテシステムは400床以上をもつ一般病院の約85%以上に導入されており、医療機関で働く人にとって電子カルテを含む医療情報システムの知識とスキルは必要不可欠なものとなってきています。
電子カルテオペレーション実務能力認定試験は文部科学省のカリキュラムに沿った「C&C電子カルテシステム」という教育用電子カルテソフト使用する試験となっています。試験を受けることで電子カルテを含む医療IT化に関する基礎知識と電子カルテの実務に必要なオペレーションスキルを習得することができます。
電子カルテオペレーション実務能力認定試験の試験内容
電子カルテオペレーション実務能力認定試に受験資格はなくどなたでも受けられます。試験の概要についてまとめると以下のようになっています。
| 試験形式 | 学科問題(マークシート方式):10問 実技問題(出力・ソフトによる診療録作成):2問 |
| 試験時間 | 学科30分・実技60分の計90分 |
| 受験費用 | 一般受験:7500円(CD-ROM版)・10000円(DL版) 団体受験:7000円 |
| 試験日程 | 3月、8月、11月の年3回 |
一般受験で受ける場合は在宅受験、教育機関や医療機関、企業から受ける場合は団体受験となり会場で受験することになります。表を見ると一般で受ける場合、CD-ROM版とDL版の金額に差があるのがわかりますね。
ヒューマンアカデミーオンライン医療事務講座
→電子カルテオペレーション実務能力認定試験をはじめ、医療事務に関する様々な資格取得を同時に目指せる講座
たのまな電子カルテオペレーション講座
→1日30分の学習で電子カルテのスキルが身につく講座
学科試験、実技試験の出題内容
学科試験と実技試験の内容についてそれぞれ以下のようにまとめてみました。
【学科試験】
| 電子カルテの基礎知識 | 電子カルテの定義について 電子カルテシステム導入時におけるチェックポイント 電子カルテシステムのメリット電子カルテシステムの機能について ・ユーザー認証 ・アクセス権限管理 ・問診票の入力等 ・電子カルテの記載方法(SOAP等) ・クリティカル・パス 電子カルテシステムの関連知識について ・部門システム(医事会計、検査部門、医用画像等) ・個人情報保護とセキュリティ ・医療情報の標準化 ・第三者評価、認証制度 ・地域医療情報システム ・電子カルテシステム関連用語 |
| 医療IT化の基礎知識 | 日本の医療制度の変遷について ・医療・健康・介護・福祉分野の情報化グランドデザイン ・診療録に関する法的要件 ・電子保存の3原則について |
【実技試験】
| 電子カルテの概念・ネットワーク 権限設定~患者受付 |
担当者登録画面における登録・権限設定 患者情報(氏名、生年月日、保険情報、入院患者属性情報等)の入力 担当医師と代行入力者の設定 代行入力者として入力、医師の承認入力 |
| 患者受付~SOAP入力 | 問診票(主訴、既往症等)の入力 症状(S)の入力 シェーマ図(人体・臓器の図、文字、線、丸囲み等)の入力 所見(O)の入力 評価(A)の入力 病名登録 計画(P)の入力 予約登録 |
| 診療内容入力 | 初診・再診料の入力 医学管理料の入力 在宅医療の入力 投薬 (院外処方)・注射料の入力 処置料の入力 手術・麻酔料の入力 検査料の入力(結果入力を含む) 画像診断の入力(結果入力を含む) リハビリテーション、精神科専門療法、放射線治療の入力 |
電子カルテオペレーション実務能力認定試験はテキストの持ち込みが不可なのできちんと勉強をし、暗記する必要があります。受験資格はないため独学で学び、受験することも可能ですが出題内容を見てわかる通り専門用語も多いので理解するのがなかなか難しいでしょう。実技試験対策に実際のソフトが使用できる通信講座での対策が一番おすすめです。
資格取得までの流れ

電子カルテオペレーション実務能力認定試験を一般受験する場合の受験申込みから合否発表までの流れを以下のようにまとめてみました。
- 試験日程と出願期間を確認の上、インターネットまたは郵便で申し込みをして受験料を支払う。
- 試験日の約10日前に受験票が到着する。
- 試験日の前日に問題用紙と解答用紙等が到着する。
- ソフトを立ち上げ、試験問題に解答する。
- 実試験日の翌日までに解答を郵便局の窓口で一般書留にて返送する。
- 合格発送予定日に合否通知が発送される。
⑤の解答の返却についてですが実技答案は受験者自身でPDFデータ化し、保存したデータを指定のメールアドレスに添付して送信しなければなりません。実技答案以外は同封されている返送用封筒に書類を入れて試験日の翌日までに返送しましょう。解答の返送時、指定の方法以外で返送すると受け取ってもらえないので注意が必要です。
また一般受験のDL版を選択した場合、試験日の約2週間前にソフトダウンロード用のライセンスキーがメールで送られてくるので試験日までにソフトをインストールして必ず動作確認をしましょう。
今後の自分の仕事のためにもしっかりと勉強して受験に挑みましょうね。
履歴書の書き方
電子カルテオペレーション実務能力認定試験に合格すると履歴書に記入し、資格の保有をアピールすることができます。
履歴書に資格を書く場合は略称でなく、正式名称で書きましょう。書き方の例は以下の通りです。
令和〇年〇月〇日 電子カルテオペレーション実務能力認定試験 合格(主催・全国医療福祉教育協会)
電子カルテオペレーション実務能力認定試験の難易度や合格率

電子カルテオペレーション実務能力認定試験の難易度は易しいものとされており、合格率も75%〜80%前後と低くはない数字です。医療事務の資格の中で一番難しいと言われている診療報酬請求事務能力認定試験の合格率は約30~40%なので電子カルテオペレーション実務能力認定試験は初級~中級くらいの難易度といえるでしょう。
試験の難易度によって変動はあるものの全体の正解率60%前後が合格ラインといわれています。詳しい採点基準は非公開です。
合格率の数字から比較的取りやすい資格に分類されるでしょう。ですがテキストの持ち込みは不可な上に実際のソフトを使用しての実技試験もあります。専門的な用語も多いので油断せず、しっかりと勉強しましょう。
まとめ
以上、「電子カルテオペレーション実務能力認定試験ってどんな試験?合格率や難易度は??」でした。
いかがでしたでしょうか。
現在の医療の現場では、電子カルテの導入など急速にIT化が進んでいます。
医療の現場で働くスタッフにはIT化の時代に対応できるような+αァのスキルまで求められるようになってきているのです。
電子カルテオペレーション実務能力認定試験は電子カルテが一般的になっている今、今後役立つ資格といえるでしょう。
今後のニーズを見据えてぜひ受験してみてはいかがですか。