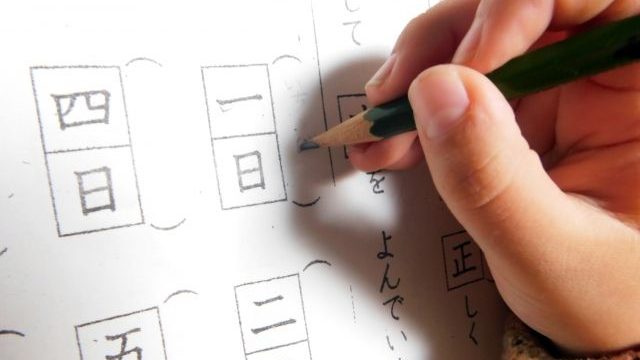ここ数年、日本では中国からのインバウンド、また中国へビジネスや留学へ行く日本人がとても増えました。
テクノロジーなどのハイテク技術、庶民が使う日用品や飲食店等などでも、日本の商品やサービスが求められています。
13億人の中国市場を求め、多くの人達が双方の国を行き交うようになりました。
特に日本の技術や協力がとても必要な業種、分野もあります。例えば下記です。
- 環境分野
- 衣食住の安全管理
- 最先端のハイテク技術
今、中国企業で活躍できる優秀な、日本人を求められています。
中国企業で働く場合、中国語が必須となってきますが、中国語とひと口に言っても、どの中国語を学べば良いのでしょうか。
最近、私が経営している飲茶Cafeに良く来る大学生から相談を受けた事例をご紹介します。
北京語を勉強していればOKなのではないんですか?
それで戸惑ったのね、でもタクシーの運転手はあなたの言葉を理解してくれたでしょ?
修学旅行で中国にとても興味を持ち、中国語を使って仕事ができないかなと思いました。
まずは中国語の資格を取りたいんですが、何がオススメですか?
北京語の簡単な会話程度ならすでにできます。
それならビジネス中国語検定をオススメします、仕事でバリバリ活かしていきたいなら、ピッタリね
Contents
中国語を勉強するなら、北京語?上海語?広東語?
中国では、昔から各地で北京語・広東語・福建語・湖南語・上海語など別々の言葉が使われてきました。
しかし、それぞれ言葉同士の違いが大きく、別な言語と思えるほどです。違う地域同士の方言は、ほとんど通じないため、中国は建国時に北京語を共通語として広めました。
中国大陸では方言の種類が80以上あり、それぞれが独立した方言、言語となっているため地域によっては、全く言葉が通じないということもあります。
北京語は日本でいう、東京弁になります。
日本で東京の言葉が標準語となるように、中国では北京語が標準語となっています。
もちろん、上海などはその歴史や文化、特徴から今も上海語は深く存在しますし、使われています。
でも上海語が使えなくて困ることはなく、やはり共通語は北京語となっています。
繁体字(はんたいじ)とは
使われる地域:台湾、香港、マカオ
特徴:正字、正体字とも呼ばれており、英語で表記される場合は”TraditionalChinese”と表現されます。
簡体字に比べ圧倒的に字数が多いですが、美しい漢字を使っているものが多いのが特徴です。
例えば、傳、團、學、醫、總など。
簡体字(かんたいじ)とは
使われる地域:中国本土、シンガポール、マレーシア
特徴:偏(へん)や旁(つくり)が簡略化され画数が少ないため書きやすい。
日本で中国語を学ぶ際の教材もほとんどが簡体字を使用しています。
ビジネス中国語検定や中国語検定も、簡体字を使用しています。
英語で表記される場合は、Simplified Chinese と表記します。
ようこそ日本へという言葉を繁体字と、簡体字に比較してみます。
- 繁体字:歡迎來到日本
- 簡体字:欢迎来到日本
観光という言葉を表すと下記です。
- 繁体字:觀光
- 簡体字:旅游
日本の漢字は主に繁体字から由来しているものが多いため、慣れると日本人にとって読みやすいのは、繁体字かもしれません。
中国語のネイティブを話す人達は、繁体字、簡体字どちらの字で書かれたものも、理解しています。
中国語検定も、ビジネス中国語検定も標準語となっている北京語の語学力をはかります。

中国語を認定する7種類の資格
この記事ではビジネス中国語検定をメインにお話ししますが、他の中国語検定のことも知っておくと、ビジネス中国語検定の特徴がよりわかります。
持っているスキルや、目標によっては、他の検定も併せて検討した方が良い場合もあるかもしれませんね😊
そこでビジネス中国語検定について説明する前に、ビジネス中国語検定を含む、7つの中国語検定をご紹介します。
それぞれの違いや、向いている人、試験自体の特徴などを比較してみましょう。
BCT (ビジネス中国語検定)
この試験が向いている人→日本企業で中国語を活用して仕事をしたい人
中国語を母国語としない人
特徴
- 中国とのビジネスにおいて中国語力を証明するパスポートのような存在
- 中国と関連する国際企業への就職・転職や昇給など関係者のビジネス中国語レベルを評価するのにとても有効的
- 日常生活の言葉というよりは、ビジネスに特化した内容
- 中国政府が実施する、世界標準の中国語力を認定する試験であり、中国語のTOEICと呼ばれている
- 国家資格になる
検定レベル:BCA(A)初級、BCA(B)中上級の2段階
年間試験回数:年に4回(4月、6月、8月、11月)
主催団体:中国政府、日本BCT事務局:セリングビジョン株式会社
ちなみに、このビジネス中国語検定試験は、そのジュニア版として、YCT(青少年中国語検定試験)というものがあります。
これは、母語が中国語ではない青少年の中国語を活用できる能力を試験します。筆記試験と会話試験の2構成になっており、1~4級までの4レベルになっています。
一番高いレベルであるYCT4級でHSK(漢語水平考試)の3級と同等、また語彙量は約600語程度と言われております。
日本では、29歳までの方が受験可能となっています。
中国語検定
この試験が向いている人→ 日本企業で中国語を活用して仕事をしたい人
特徴
- 日本国内では、一番認知度が高く、受験者数も多い検定
- 中国語を扱う日本企業に就職したい人向け
- 中国語検定1級はかなり難易度が高く、中国語のネイティブでも難しいと言われています。
求められる能力: 日本語と中国語の相互通訳、翻訳能力
検定のレベル:1級・準1級、2級、3級、4級、準4級の6段階 (1級が一番レベルが高い)
年間試験回数:1年に3回、1級のみ年に1回
主催団体:一般財団法人 日本中国語検定協会
HSK(漢語水平考試)
この試験が向いている人→ 中国への留学や出張、中国で就職がしたい人
特徴
- 中国政府教育部直属の機関が主催しており、成績報告は、中国、日本国内、世界中で公的証明として活用する事が可能
- 試験会場が日本、中国以外に世界118国で実施されている
- 企業の駐在員に対しては、中国の外国人労働者に対するランク付けがある(点数制によって労働許可の条件が変わる仕組み)
- HSK資格が就労ビザの発給にもプラスになります
- 中国での仕事をしたいと思う方は、ぜひ視野に入れて欲しい試験
- 主に大学生や社会人を対象とする中国語のアカデミックな要素が強い
- 高い実用性のある中国語をはかる
求められる能力:リスニング、読解力、3級以上からは作文能力が入ります。
出題言語も回答も全てが中国語で展開されます。
検定のレベル:初級が1級〜上級の6級まで、6段階
年間試験回数:年に1回、2022年度は6月12日実施予定
主催団体:中国政府教育部 孔子学院总部/国家汉办
TOCFL(華語文能力測験)
この試験が向いている人→主に台湾での就職や台湾とのビジネス取引、仕事をしている人
中国語(台湾華語)を母国語としない台湾華語能力試験
特徴
- 繁体語を使用している試験
- 台湾奨学金を申請する為の参考基準
- 外国人留学生を募集している台湾の大学
- 台湾の専門学校等において中国語能力の参考基準として
- 台湾における就職活動をする際の中国語能力の証明として
検定レベル:Band A(入門→レベル1、基本級→レベル2) , Band B(進階級→レベル3、高階級→レベル4) , Band C(流利級→レベル5、精通級→レベル6)、6つのレベルがあります。
年間試験回数:2022年は、1/23、2/27、3/27、5/29、8/28、11/27
受験地も全国9か所で行われますが、地域によっては年に一回の所もあります。
お近くの受験地とスケジュールを確認してください。
主催団体:台湾の国家中国語能力試験推進委員会
参考:https://tocfl.jp/
全国通訳案内士
この試験が向いている人→中国語のツアーガイドになりたい人、語学力だけでなく幅広い知識を身につけたい人、中国語の語学の国家資格が欲しい人
特徴
- 全国通訳案内士は、中国語をはじめフランス語、英語など10ヶ国語が認定
- 現在日本を訪れる外国人の中で、中国人が一番多いが中国語を話せる人が慢性的に少ないためコミュニケーションを取りながら案内できる人材
- 今では観光だけでなく、日本の最先端医療を求めて来日する中国人も増加傾向
- 国家資格であるが受験資格などなく、誰でも受験可能
検定レベル:合格率10%~15%と言われている
年間試験回数:年に1回、8月に一次試験、2月に二次試験の面接がある
主催団体:観光庁
参考:https://www.jnto.go.jp/jpn/projects/visitor_support/interpreter_guide_exams/copy_of_index.html
C.TEST (実用中国語レベル認定試験)
この試験が向いている人→実践での会話力を測りたい人、中国で仕事をしたい人
特徴
- 実践的な中国語力を測定する試験である
- 留学以外の目的で中国語を学んでいる人のために開発された新たな国際的な試験
- 基礎からビジネスまでの、即答できるコミュニケーション能力をはかる試験
- ヒアリングを重視としている
- インターネットのテレビ会議ツールを活用して、面接官と実際に会話をするという方法を取り入れている
検定レベル:A~Dレベルと、Gレベル、2通りの試験
年間試験回数:年に3回、3月、9月、11月
主催団体:北京語言大学漢語試験研究センター
TECC(中国語コミュニケーション能力検定)
この試験が向いている人→シーンに関わらず、中国語でコミュニケーションを重視したい人
特徴
- 2021年6月よりオンラインテストへと移行されたため、自宅からの受験が可能になりました
- 易しい問題から高難易度の問題まで幅広く網羅した内容となっています
- 1000点満点で自分のレベルをチェックできるため、中国語の基礎力がどれぐらいあるのかチェックするのに最適です
- 出題内容も日常生活やビジネスなどで、よく使われる中国語
検定レベル:1000点満点で点数がスコア化されます
年間試験回数:年に2回、第3回→6月19日
主催団体:株式会社 空間概念研究所
仕事をするために、高いスキルをつけると考えるなら、ビジネス中国語検定試験または、HSKがおすすめです。
HSKとビジネス中国語検定試験のスキルマップ
| 語彙量 | BCT(ビジネス中国語検定試験) | HSK(漢語水平考試) |
| 5000語以上 | BCT (B)中上級 | HSK (6級) |
| 2500語程度 | HSK (5級) | |
| 1200語程度 | HSK (4級) | |
| 600語程度 | BCT (A)初級 | HSK (3級) |
| 300語程度 | HSK (2級) | |
| 100語程度 | HSK (1級) |
日本で中国語を使う企業に勤めるならビジネス中国語検定試験が良いです。
先々、中国にも度々行ってビジネスの交渉や、駐在したりするならプラスでHSKも受験しておくのをオススメします。
HSKはビザ申請などにもプラスになりますので、中国関連や中国勤務の仕事を探す際には大変有利な資格となります。
ただしHSKは、出題言語も回答も全てが中国語で展開するため、ある程度高い水準の中国語力を身につけてから受験すると良いでしょう。
勉強しやすく、実力をつけやすい流れとしましては下記をご参考にしてください。
- YCT(青少年中国語検定試験)を受験
↓ - HSK(漢語水平考試)を受験
↓ - ビジネス中国語検定試験 を受験。
ビジネス中国語検定ー受験の流れ
受験から合格までの大まかな流れは、以下のようになります。
- インターネットで申し込む
- 受験料を支払う
- 受験票をプリントアウトする
- 試験当日
- 合格発表
受験の流れは特に難しくないです。基本的にはネットで申し込みや準備をします。
では、上記で挙げた項目の詳細を以下に説明していきたいと思います。
①申込受付期間内にインターネットで申し込む
試験日:第一回目6月18日(土曜) 東京のみ
受付期間:3/28~ 5/20 必着
試験日:第二回目11月19日(土曜)東京、名古屋、福岡
受付期間:8/19~ 10/14 必着
下記から申込(申込フォームの仕様上Googleアカウントが必要です)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIhbUqmjnO8RHTEnCuplxgMET6fY35xNcPLC1WL1gjjcAvAg/viewform
申込書で申し込みをする場合は、こちらからダウンロード可能です。
https://www.bct-jp.com/pdf/2022-bctyct.pdf
②申し込みの際に、受験料も支払う
- 申し込みは、受験料をカード払いをして完了となります。
受験料
- BCTーA:5,000円(税込)
- BCTーB:8,500円(税込)
- カード払いができない場合
下記口座宛に振込みお願いします。
三菱UFJ銀行 神田支店 店番331 普通預金 0510628
トクヒ)ゼンニツポンチユウゴクゴキヨウイクキヨウカイ
BCT検定運営センター 特定非営利活動法人全日本中国語教育協会
- 振込依頼人名欄に受験者名をご入力してください
- 振込手数料はご負担いただきますようお願いします
カード払いも、振り込みも受験料支払い完了後は、返金やキャンセル、払い戻しはできません。
③受験票をプリントアウト、サイトログインの注意点
試験日の2週間前までにはサイトへログインし、受験票をプリントアウトしてください。
フォームからではなく申込書で申し込む方
下記から申込書をダウンロードしてください。
https://www.bct-jp.com/pdf/2022-bctyct.pdf
- 申込書を印刷
- 記入事項を記載
- 受験料を申込書にある事務局の口座へ振り込む。
振り込みの際に発行される振込の証明書と顔写真(タテ4cm✖️ヨコ3cm) 1枚を所定の場所へ貼り付ける - 事務局へ郵送。
試験の約2週間前に受験票を送付いたします。
受験当日、必ず受験票を持参してください。受験票が無い場合は試験会場に入れません。
④試験当日
試験当日、必ず受験票を持参してください。
受験票がなければ会場に入ることはできません。
試験時間割(2022年度予定)
| 級別 | 試験時間 |
| BCT (A) | 11:00~12:10 |
| BCT (B) | 13:00~15:25 |
⑤合格発表
試験の成績は約1ヶ月後に、BCT検定試験センターの公式サイトにて発表します。
BCT検定試験センター(全日本中国語教育協会)
https://www.bct.center/result
マイアカウントにログインしてから確認し、ご自身で印刷してください。
成績有効期間は2年です。
成績報告には、合格点とは設定されていないため、受験者の科目ごとの得点と総合得点が記載されます。
ビジネス中国語検定試験の出題内容、難易度や合格率まで
ビジネス中国語検定試験の出題内容は、3科目です。BCTーA(初級)と、BCTーB(中上級)では、3科目めの内容が異なりますので、注意して確認してください。
出題内容や配分について
出題内容や、それぞれの時間配分についてご説明します。
BCTーA(初級)
| 試験項目 | 問題数 | 解答時間 | 点数配分 |
| ⒈ヒアリング | 30問 | 約20分 | 100点 |
| ⒉読解 | 30問 | 約30分 | 100点 |
| ⒊漢字を書く | 10問 | 約10分 | 100点 |
| 合計 | 70問 | 60分 | 300点 |
- ヒアリングは、4つの問題から選ぶ四肢択一式です
- 漢字は、文の意味を理解して文中の空白に当てはまる漢字を書きます。
BCTーB(中上級)
BCTーB(中上級)では、3項目めに漢字が出題とされていたのが、作文になります。
| 試験項目 | 問題数 | 解答時間 | 点数配分 |
| ⒈ヒアリング | 50問 | 35分 | 100点 |
| ⒉読解 | 40問 | 60分 | 100点 |
| ⒊作文 | 2問 | 40分 | 100点 |
| 合計 | 92問 | 135分 | 300点 |
- ヒアリング:文や会話、スピーチを聞いて、適切な解答を選択する
- 読解:適切な語句や文を選択する問題、質問に対する解答を選択する問題
- 作文:文や図表を理解して、適切な作文を書く記述式問題
出題形式とは
出題形式は、BCTーA(初級)と、BCTーB(中上級)は、どちらも出題形式は似ています。
内容の難易度や、問題数、解答時間が異なります。
上記の表を参考に下記を参考にしてください。
ヒアリング
3種類の問題があります。
- 語句や短いフレーズが放送され、その内容が写真の内容と一致するかどうかを判断する
- 短文が放送され、3枚の写真の中から内容と一致するものを選ぶ
- 2人の会話とその会話の内容に関する問いが放送され、問いの答えとして、正しいものを3つの選択肢から選ぶ
- 四肢択一式、穴埋め問題
読解
- 文中の空所部分に、選択肢の中から適切なものを1つ選ぶ
- 3つの質問と3つの返答が与えられており、質問と返答の内容が対応するものを選ぶ。
漢字を書く/中上級では作文
- 文の意味を理解して、文中の空所に当てはまる漢字を書く(初級)
- 文や図表を理解して、適切な作文を書く問題(中上級)
難易度や合格率はどうなの?
ビジネス中国語検定は、中国語のTOEICと呼ばれております。
明確な合格率や難易度を公開しておりません。
ただ初級でも、しっかり勉強していないと合格は厳しい試験と言えます。
ヒアリングや読解に関しては、HSKよりやや易しいとは言われております。
下記をご参考にしてみてください。
ビジネス中国語検定試験の成績は合否ではなく、3つの科目において(ヒアリング、読解、作文)それぞれ100点満点のスコアによって示されます。
ここではそれぞれの科目でという認識でいてください。
| 点数 | 通用するレベル |
| 80点以上 | 中国ビジネスへの対応が十分可能なレベル |
| 70点~79点 | 中国ビジネスへの対応が基本的に可能なレベル |
| 60点~69点 | 中国ビジネスへの対応が初歩的に可能なレベル |
| 50点~59点 | 中国ビジネスへの対応が今一歩のレベル |
| 50点未満 | 中国ビジネスへの対応が不十分なレベル |
中国語を使って仕事をしていきたい場合は、BCT-(B)中上級、70点以上を目標にしてください。

勉強方法は?
この記事を読んでくれている方は、ご存知かと思いますが、中国語は基本の発音が命と言われています。
中国語は発音の四声(しせい)を制することで、中国語を制することができるという先生も少なくありません。
また日本人には出しにくい発音が膨大にあります。
言語を習得するには、読む・聴く・書く・話すといった4技能をバランスよく身につけていくことが重要と言われています。
聴く、話すということが得意になれば、書く、読むということは参考書や文献でも独学で勉強が可能になります。
四声の発音を重点的に、基本だけでも通学をオススメします。
もちろん、ある程度勉強している方でも、ハイレベルな語学力を身につけたいなら、基本を徹底するためにも、聴く、話すということはネイティブへの確認ができる方法をとるのをオススメします。
中国語は基本の四声(しせい)を最初に、徹底して習得することで、後々の勉強がとてもやり易く、伸びるのも速いです。
予算や、スケジュール的に通学が無理な場合は、音声CDなどがついた教材をお使いになると良いです。
教材であれば、その1冊を何度も何度も、聴きながら、聴く、話す、読む、書くということを、繰り返すことです。
勉強していた時は、日本語で言えば五十音のようなもののなのに、難しくてそれを継続するのが大変でした。
これから中国語をレベルアップしていくにも、この4声の発音を継続して徹底するといいわね。
中国語の基本となる四声の発音とは?
中国語を勉強する方々から、この中国語の基本の発音をとても難しいという声が多いです。
ここでは、効率的に学習していくためにも、この基本の発音である四声について少し深掘りしていきましょう。
日本語では複数の音節間で上がったり・下がったりという高低があります。これに対し中国語は、一音節のなかでこの高低という抑揚をつけます。
中国語は全て漢字で表記されますが一つの漢字の発音が一音節となります。
これはアクセントという二つの要素で「声調」といいます。
声調は四種類あるので「四声」と呼ばれています。
声調符号はピンインの頭につけられ、発音はピンイン[拼音:pīn yīn]と四声で表されます
| 第一声 | 第二声 | 第三声 | 第四声 | |
| ピンイン | [ mā ] | [ má ] | [ mă ] | [mà ] |
| 例 | 妈 | 麻 | 马 | 骂 |
| 声の声調/構造 | → | ↗︎ | ↘︎↗︎ | ↘︎ |
| 意味 | 母、お母さん | あさ | 馬 | 叱る、罵る |
うわぁ、改めてこうやって見ると、ま一つ取っても、その声調が違うだけで、これだけ意味が全く異なるってすごいですね!!
ビジネス中国語検定試験は履歴書に書けるの?
ビジネス中国語検定試験は、中国語検定やHSKと違い、◯級という事ではありませんが、履歴書には書けます。
例えば、BCTーB、250点など、AかBである事と、点数を記載してください。
ビジネスで有利にするには、BCTーB、200点以上は目指しておくと良いでしょう。
中国語関連企業への就職や、ビジネスで中国語が必要な会社への就職、転職ではとても有利な資格になります。
合格時に成績証明書をプリントアウトしておけば、履歴書と一緒に提出することもできますので、合格したら必ずプリントアウトはしていてくださいね。
中国語を含むマルチリンガルな人材
日系企業が盛んに中国へと進出していた、2000~2010年頃までは、語学力さえあれば専門性が浅くても、すぐに採用される時代だったようです。
ところが、それから10年あまりの間に雇用や進出も落ち着き、中国自体も文化、経済と共に発展しました。
今は、高い語学力プラス、専門性が問われます。
もちろん、国が違えば同じアジアといえど、働き方や、考え方、文化などを含め、日本と中国、海外では全く異なります。
そこでも高い語学力を備えていれば、コミュニケーションが取れますので、そこは乗り越える強力なスキルとなります。
日本人の細やかな気遣いは、中国に関わらず海外でも高い評価を得ています。
特に、ビジネスの現場においては実践的な日本語会話能力が重要となっていきます。
外国人特有の訛りやイントネーションなどは特に慣れて行けば問題はないかと思います。
しかしながら、日本語特有の曖昧な言い回しを理解しましょう。
例えば「大丈夫です」「結構です」など、これらは日本では良く聞こえてくる言い回しです。
しかし、このOKとNOの両方の意味がある表現は、中国に関わらず、アメリカ、ヨーロッパにおいても理解され難いものです。
わからない場合や、相手が戸惑っていると感じた場合は、聞き返したり認識を確認したりなどの柔軟なコミュニケーション能力が必要不可欠です。
まとめ
この記事を書いている私自身が、昔、仕事で中国へ行った際に、人々がとても好奇心旺盛なことにびっくりしました。
何か一つ、わからない事があって街の人や、会社の人に聞くと、周囲から人が集まり、すぐに人だかりになりました。
そして、あちらから、こちらから多くの人達がそれぞれの見解で発言し合っていくのを呆気に取られて見ていましたが、同時に面白いと思いました。
語学ができてコミュニケーションが取れると、とても楽しく仕事ができると思います。
一つ、私個人的にオススメなことは、四声を使い分ける中国人達は耳が良いのか、カラオケがとても上手な人が多いです。
ぜひ、1曲だけでも良いので、中国語で歌える曲を身につけてみてください。
語学を勉強する際に、その言葉で歌を覚えるのはとても有効的です。
さらに、さまざまな場面でコミュニケーションが取りやすくなります。
今回は、下記についてご案内しました。
- 中国語を勉強するなら、北京語?上海語?広東語?
- 中国語を認定する7種類の資格
- HSKとビジネス中国語検定試験のスキルマップ
- ビジネス中国語検定ー受験の流れ
- ビジネス中国語検定試験の出題内容、難易度や合格率まで
- 勉強方法は?
- ビジネス中国語検定試験は履歴書に書けるの?
- 中国語を含むマルチリンガルな人材
- まとめ
あなたの未来にお役に立てることができれば、大変うれしいです🐼🌿