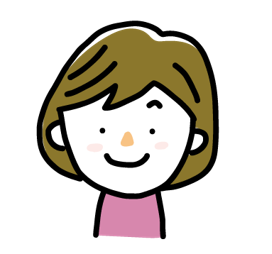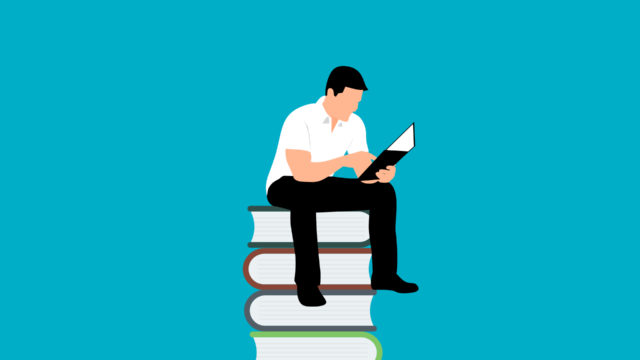フランス語検定と聞いても漢検や英検といったメジャーなイメージはなくどんな検定でどれくらい難しいのか、メリットはあるのかたくさん疑問が出てくるのではないかと思います。
この記事ではそんなフランス語検定について
- フランス語検定とはなにか
- 3級~5級のレベルや難易度
- 必要な勉強時間
- 取得のメリット
以上のことを解説していきます。興味のある方はぜひ最後まで読んでいってください。
Contents
フランス語検定ってなに?

フランス語検定は「実用フランス語技能検定試験」のことで仏検と略されることもあります。公益財団法人フランス語教育振興協会が年に2回実施しており、フランス語の実用能力を測ることができる日本独自の検定試験です。
フランス語は外交では英語に次いで最も使用されている言語で国際オリンピック委員会の公用語として英語とともに認定されています。
5級、4級、3級、準2級、2級、準1級、1級の7段階にレベル分けされており準2級からは筆記試験に加えて口頭試験(面接)も行われます。今回の記事では5級~3級までを詳しく解説していきます。
フランス語検定(3級、4級、5級)のレベルや難易度、勉強時間
それでは各級のレベルや合格までに必要な勉強時間をみていきましょう。
5級のレベルや難易度、勉強時間
フランス語検定5級を合格するのに必要な勉強時間は50時間以上とされており語彙数は550語程度です。フランス語検定の中では入り口とされる難易度で最も易しいレベルになります。試験内容は以下の通りです。
| 読む | 初歩的な単文の構成と文意の理解、短い初歩的な対話の理解 |
|---|---|
| 聞く | 初歩的な文の聞き分け、挨拶等日常的な応答表現の理解、数の聞き取り |
| 文法 | 初歩的な日常表現の単文を構成するのに必要な文法的知識。動詞としては、直説法現在、近接未来、近接過去、命令法の範囲内 |
※仏検引用
筆記(60点)、聞き取り(40点)の100点満点の試験で合格基準点は60点、マークシート方式の選択問題となっています。
初歩的なフランス語の理解を求められている試験内容になりますね。毎日1時間の勉強、約2か月の対策で合格できるレベルでしょう。合格率は毎年約80~90%と低くない数字です。
4級のレベルや難易度、勉強時間
フランス語検定4級を合格するのに必要な勉強時間は100時間以上とされており語彙数は920語程度です。5級と比べると勉強時間が約2倍になりましたね。フランス語を趣味としてではなく語学学習を目的とした人向けのレベルになります。試験内容は以下の通りです。
| 読む | 基礎的な単文の構成と文意の理解。基礎的な対話の理解 |
|---|---|
| 聞く | 基礎的な文の聞き分け、日常使われる基礎的応答表現の理解、数の聞き取り |
| 文法 | 基礎的な日常表現の単文を構成するのに必要な文法的知識。動詞としては、直説法(現在、近接未来、近接過去、複合過去、半過去、単純未来、代名動詞)、命令法等 |
※仏検引用
表を見ると求められる文法の知識が増えているのがわかりますね。筆記(66点)、聞き取り(34点)の100点満点の試験で合格基準点は60点、こちらもマークシート方式の選択問題となっています。合格率は毎年約70~80%くらいで5級に比べると少し低くなりますがまだ合格を目指しやすい数字ではあるでしょう。4級では基礎的なフランス語の理解力が求められるレベルとなっています。
3級のレベルや難易度、勉強時間
フランス語検定4級を合格するのに必要な勉強時間は200時間以上とされており語彙数は1670語程度です。5級や4級に比べて勉強時間と語彙数がだいぶ増えましたね。旅行先での食事の注文などフランス人との簡単な会話ができるくらいのレベルです。試験内容は以下の通りです。
| 読む | 日常的に使われる表現を理解し、簡単な文による長文の内容を理解できる |
|---|---|
| 聞く | 簡単な会話を聞いて内容を理解できる |
| 書く | 日常生活で使われる簡単な表現や、基本的語句を正しく書くことができる |
| 文法 | 基本的文法知識全般。動詞については、直説法、命令法、定型的な条件法現在と接続法現在の範囲内 |
※仏検引用
3級では長文の内容の理解を求められ「書く」という項目も増えています。筆記(70点)、聞き取り(30点)の100点満点の試験で合格基準点は60点、同様にマークシート方式の選択問題ではありますが「書く」という項目が増えたことにより一部記入が必要なものも含まれています。合格率は毎年約50~60%。5級や4級に比べてぐっと下がりますね。ですが2人に1人は合格できる数字です。
フランス語検定の実施日程や検定料

フランス語検定は春と秋の年2回行われており一次試験と二次試験というものがあります。二次試験は準2級から追加で行われる口頭試験(面接)のことですね。準2級からは一次試験の筆記試験で合格した人のみ二次試験に進むことができます。春季と秋季の日程を表にまとめてみました。
春季
| 実施級 | 1級 2級 準2級 3級 4級 5級 |
| 実施日程 | 一次試験 2022年6月19日 |
| 二次試験 2022年7月17日(1級・2級・準2級の一次試験合格者のみ) | |
| 申込期間 | 2022年4月15日〜5月18日(願書郵送の場合) |
| 2022年4月15日〜5月25日(インターネットの場合) |
秋季
| 実施級 | 準1級 2級 準2級 3級 4級 5級 |
| 実施日程 | 一次試験 2022年11月20日 |
| 二次試験 2023年1月22日(準1級・2級・準2級の一次試験合格者のみ) | |
| 申込期間 | 2022年9月上旬〜10月19日(願書郵送の場合) |
| 2022年9月上旬〜10月26日(インターネットの場合) |
※2022年6月の時点での情報です。
上の表を見てもらうと1級と準1級に関してはそれぞれ年に1回しか試験を受けるチャンスがありません。計画的に勉強を進めて合格したいところですね。各級の検定料は以下の通りです。
| 1級 | 13,500円(春季) |
| 準1級 | 11,500円(秋季) |
| 2級 | 9,000円 |
| 準2級 | 8,000円 |
| 3級 | 6,000円 |
| 4級 | 5,000円 |
| 5級 | 4,000円 |
級が上がるにつれて検定料も高くなっていますね。5級と4級、4級と3級といった併願もすることができ、その場合の検定料は2つの検定料の合計から1,000円割引がされます。
例:5級と4級の併願(4,000+5,000-1,000=8,000円)
受験資格に制限はなくどなたでも受けることができます。
フランス語検定の勉強法のポイント

フランス語はイタリア語やスペイン語といったラテン系言語であり日本人にとって馴染みが薄い言語です。文法や発音も難しく難易度が高く感じる検定ではあるでしょう。しかし英語と類似している点もあり英語学習者にとっては意外と簡単に感じることも多いです。ではどういったポイントに注意して学習を進めていけばよいのでしょうか。以下にまとめてみましたのでぜひ参考にしてみてください。
発音はスペル通りでよい
フランス語は発音が難しいと前述しましたが基本的にはスペル通りの発音で問題ありません。例えばdoubt(疑う)の発音はダゥトですよね。英語の場合こういったスペルと発音の仕方が一致しない(この場合はbの部分を発音しない)といったものがフランス語にはほとんどないのでスペル通りの発音でよいというわけです。
ではなぜ難しいと言われているのでしょうか。フランス語は日本語と違って独特な発音であり、親しみのない言語だからです。英語と違って耳にする機会も少なく経験値の差が難しさのハードルを上げているということもあるでしょう。ですがフランス語の発音は英語に比べると規則的であり、最初に正しい読み方や発音の規則を覚えてしまえば発音の勉強もスムーズに進めることができるでしょう。
おすすめの勉強法、教材→やさしいフランス語の発音
こちらの教材はMP3CD付きです。テキストを見ながら繰り返し聞いてフランス語に耳を慣れさせましょう。
文法の基礎固めはしっかり
フランス語の基礎は文法であり、とても需要な部分です。
フランス語の単語には名詞に性別があったり動詞の活用は英語よりも多いです。不規則活用動詞も少なくなく、時制も躓きやすいポイントです。ですが英語と似ている語彙も多く類似性を見つけて楽に覚えられるよう意識するのがおすすめです。文法は勉強の土台となる部分なので丁寧に取り組み確実に理解をして勉強を進めていきましょう。
おすすめの勉強法、教材→フラ語入門、わかりやすいにもホドがある! [改訂新版]《CD付》
初心者向けで教科書にように使える一冊です。反復し、完璧になるまで勉強しましょう。
単語やイディオムの暗記
語学学習の進行には単語の暗記は必須です。発音や文法の勉強と並行して少しずつ進めていきましょう。またイディオムを覚えることによってフランス語の理解力が深まりモチベーションの維持にもつながります。通学や通勤時間などの隙間時間を利用して学習を進めるといった意識が大切です。
おすすめの勉強法、教材→CDブック これなら覚えられる! フランス語単語帳
単語の暗記は短期間でまず一周し、記憶が残っているうちにくり返し読む勉強法がおすすめです。
リスニング力も鍛えよう
コミュニケーション力の向上や聞き取り対策のためにリスニングの練習にも取り掛かりましょう。はじめのうちはなかなか聞き取れず不安になるかと思いますが毎日フランス語に触れていくうちに耳も慣れ、聞き取れるようになってくるので心配はいりません。少しでも早く慣れるためには継続が大切なので毎日少しの時間でもフランス語を聞くようにしましょう。映画やyoutube動画を活用して楽しく学習するのがおすすめです。
おすすめの勉強法→紹介した教材に付いているようなCDを繰り返し聞くことがリスニング力向上に一番効果的です。その際「聞き流し」はせずに集中して聞くようにしましょう。
フランス語検定のメリット

ここまでフランス語検定の難易度や試験内容について説明しましたがではいったいどんなメリットがあるのでしょうか。
フランス語話者は意外と多い
日本人にとっては馴染みが薄いフランス語ではありますがフランスだけでなくカナダやモロッコといったアフリカ諸国など多くの国で活用されています。フランス語の勉強が多くの人とのコミュニケーションのきっかけにもなり、旅行や就職先で役立つことは間違いないでしょう。
学生の場合、単位取得や留学に有利になる
フランス語学科がある大学ではフランス語検定を取得すると単位をもらえる制度がある場合があります。3級(4単位分)や準2級(6単位分)が取得の目安です。AO入試でも役に立ったりするのでこういう明確なメリットがあると学習のやる気が出ますよね。また交換留学する場合、休学せずに単位が取得できるので検討している人はフランス語検定の受験をおすすめします。
通訳案内士の語学試験が免除になる
通訳案内士の試験は通訳ガイドとして働くための国家試験であり、フランス語検定1級を取得した場合筆記試験が免除されます。フランス語の通訳案内士の試験とフランス語検定1級の難易度がほぼ同レベルと言われてるためです。通訳士を目指している人にとっては大きなメリットであり2つの資格を所持しているというのは就活等において大きなアピールポイントにもなりますね。
就職や転職において武器になる
昨今のグローバル社会ではフランスを含めさまざまな海外企業が日本に進出しています。英語+αが求められる世の中で活躍するためにもフランス語検定は持っていて決して損はない資格でしょう。3級や4級でも履歴書に記載可能であり語学力のアピールになります。フランス語が生かせる職業としては以下のようなものが挙げられます。
- 航空会社
- 通訳、案内士
- 観光業
- 塾講師
- 商社など
グローバル化が進むビジネスシーンにおいてフランス語検定は語学力の具体的な証明として就職や転職活動、スキルやキャリアアップを後押しするでしょう。
まとめ
以上「フランス語検定をおしえて!3級、4級、5級のレベルや難易度、勉強時間は?」でした。
フランス語検定は語学力をアピールするのに英検やTOEICなどの英語+αに第二外国語として取得するのもおすすめです。少し検定料が高く感じるかもしれませんがそれ以上に大きなメリットがあると言えるでしょう。
ぜひまずは評価されやすい3級を目指して勉強を進めていきましょう。