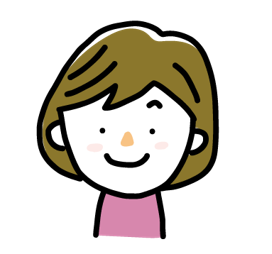DVや虐待などの被害にあったり事故や災害の記憶からトラウマを抱えている人、仕事や学校で生活でストレスを抱えている人など現在社会には様々な悩みを抱えている人がたくさんいますよね。いまこの記事を読んでいるあなたも心に問題を抱えているのかもしれません。
そんな人たちの悩みを解決に導いていく臨床心理士という職業があります。解決に導くといってもどんな方法で心の治療をしてくれるのか、実際どんな仕事をしているのか、資格の取り方など気になることはたくさんありますよね。
この記事では
- 臨床心理士の仕事
- 資格の取り方
- 試験の難易度や合格率
- 通信や独学でも可能なのか
- どんな人が臨床心理士に向いているのか
といったことを解説していきます。
臨床心理士の職業について気になる人はぜひ最後まで読んでいってくださいね。
Contents
臨床心理士という仕事

臨床心理士とは冒頭でも言ったように心に問題を抱えている人に心理学の知識を駆使してアプローチをし、解決に導いていく仕事をしている人です。心理学に携わる仕事をしている人は日本では心理カウンセラー、セラピスト、心理相談員といったさまざまな名称で呼ばれていますよね。臨床心理士もこれらのうちの一つであり、唯一日本臨床心理士資格認定協会の認定をうけている心理専門職なのです。
業務内容
臨床心理士の業務は大まかに以下の4ステップで構成されています。
- 臨床心理査定(アセスメント)
- 臨床心理面接(カウンセリング)
- 臨床心理的地域援助
- 調査と研究活動
それぞれの内容について解説していきます。
①臨床心理査定(アセスメント)
臨床心理士の仕事はまず臨床心理査定から始まります。臨床心理査定とは心理テストや面接を行うことでクライエントの今の心理状況を把握することです。本人が自覚していない悩みや不安、問題を明らかにして今後の援助の方向性を決めていきます。
②臨床心理面接(カウンセリング)
臨床心理査定の結果をもとにクライエントの心のサポートをするプロセスに入っていきます。臨床心理士の活動の中心といえる業務ですね。カウンセリングと聞くと「話を聞く・聞いてもらう」といったイメージが強いかもしれません。ですが心理療法には行動療法や芸術療法、集団心理療法などたくさんありその人に合った療法を見つけるのも臨床心理士の仕事です。
③臨床心理的地域援助
臨床心理士の仕事はカウンセリングをして終わりというわけではありません。例えばDVや虐待の問題を抱えている場合、本人の心のケアだけでなく家庭環境の問題を解決しなければなりませんよね。いじめ問題に関しては学校側と協力して問題解決のための取り組みも必要となってきます。
臨床心理士は必要に応じて自治体や学校と協力をして地域の人々が健康的な心理状態を保つための援助を行ったりするのです。この活動を臨床心理的地域援助と言います。
④調査と研究活動
①~③の一連の仕事のほかに調査と研究活動も行います。心理学は常に新しい情報が生まれており、過去の症例の知識や療法では最新の症例に対応できなくなってくるからです。臨床心理士には新たな知識を取得し学び続ける姿勢が求められているのです。
クライエントがどのような問題を抱えているのか適切に理解し、最適な療法を用いてクライエントが自力で自分の悩みや問題を解決できるよう援助する。これが臨床心理士の大切な使命であり仕事なのです。
「臨床心理士」と「公認心理士」の違い
2017年に公認心理士という心理学の新しい国家資格が定められました。
この2つの違いは国家資格であるかどうかであり現段階(2022年)で役割や仕事内容に大きな差はありません。(臨床心理士は民間資格)
臨床心理士の資格の取り方
臨床心理士になるには受験資格を満たし、本臨床心理士資格認定協会が実施する試験を受けて合格しなければなりません。そこで臨床心理士になるために必要な受験資格や資格の取り方を紹介していきます。まず流れとしては以下の通りになります。
- 高校卒業
- 大学卒業
- 指定大学院(第一種・第二種)または専門職大学院を修了
- 臨床心理士の資格認定試験を受験し合格
- 資格認定証書の交付手続きを完了し、臨床心理士へ(5年ごとに資格更新)
大学卒業後、日本臨床心理士資格認定協会が指定する大学院を修了しなければならないのですが大学院を受験するには四年制大学を卒業していなければなりません。指定大学院は修了してすぐに試験の受験が可能な第一種と、修了後に実務経験を1年以上経てから受験可能な第二種と二種類あります。
指定大学院・専門職大学院一覧はこちらを参考にしてください。(引用元:日本臨床心理士資格認定協会)
指定大学院または専門職大学院を修了後、日本臨床心理士資格認定協会が行う試験に合格して臨床心理士の資格を取得することができます。資格取得後は研修や研究が義務付けられており、5年ごとに資格の更新が必要となっています。
ここまで資格取得までの流れを説明しましたが受験資格をまとめると以下の通りです。
- 指定大学院(1種・2種)を修了し、所定の条件を充足している者
- 臨床心理士養成に関する専門職大学院を修了した者
- 諸外国で指定大学院と同等以上の教育歴があり、修了後の日本国内における心
- 理臨床経験2年以上を有する者
- 医師免許取得者で、取得後、心理臨床経験2年以上を有する者
(引用元:日本臨床心理士資格認定協会)
独学でも取得できる?
残念ながら臨床心理士の資格は上記の受験資格から独学では取得することができません。臨床心理士だけでなく心理学系の職業に利用できるほかの資格も大学で心理学を学ぶ必要があるものがほとんどです。
しかし心理学系の資格はたくさんあり独学や通信講座で取得できるものもあります。「今の職業に+αとして心理学を学びたい」、「人の話をうまく聞けるようになりたい」といった場合であれば独学で取得可能なものでも十分活用できるでしょう。
その際のおすすめの資格をいくつか挙げておきます。
| メンタルヘルス・マネジメント検定 | メンタルヘルス・マネジメント検定試験 | 働く人たちの心の健康と活力ある職場づくりのために (mental-health.ne.jp) |
|---|---|
| JADP認定メンタル心理カウンセラー | メンタル心理カウンセラー資格 | 日本能力開発推進協会 (JADP) (jadp-society.or.jp) |
| 心理学検定 | 【公式】心理学検定 (jupaken.jp) |
臨床心理士と通信大学

昼間の大学に通うのが一般的ですが指定大学院の中でも通信制や夜間を設けている大学院もあります。臨床心理士の受験資格を得ることができる通信制の大学院は以下の通りです。
- 東京福祉大学大学院(群馬キャンパス)
- 人間総合科学大学大学院(さいたま市)
- 佛教大学大学院(京都市)
- 吉備国際大学大学院(岡山県)
- 放送大学(千葉県)
一番下の放送大学だけは第二種になるため修了後は一年以上の実務経験が必要となります。5校すべてが私立大学であり、残念ながら国立大学院の中で臨床心理士の受験資格を通信で取得できるところはありません。
基本は通信での勉強になりますがどの大学院も年に平均10日ほどは対面授業が行われています。また必要に応じて臨床心理士が働いている現場で学習する期間を設けている大学院もあります。
通信課程で取得する際の注意点
通信課程と通学過程の違いを簡単にまとめると以下のようになります。
| 修了期間 | 対面授業・実習の有無 | |
| 通学過程 | 2~3年 | 必須 |
| 通信課程 | 3~4年 | 必須 |
表を見ると通学過程より通信課程のほうが修了期間が長いことがわかります。その上通信課程であっても完全なオンラインのみではなく対面授業や実習も行われます。
仕事をしながら取得を目指す場合、対面授業や実習のためにまとまった休みを取る必要が出てくるでしょう。費用面でいうと通学過程より通信課程のほうが安く済ませられますが在籍期間が長くなったり対面授業や実習の有無など注意しなくてはなりません。
臨床心理士試験の内容と費用
臨床心理士の資格取得のための試験は正確には資格審査と言われており、年に1回行われます。10月に実施される一次試験(筆記試験)と11月に実施される二次試験(口述試験)でワンセットです。合格発表は12月中旬ごろとなっています。
※2022年8月現在の情報になります。日時の詳細は必ずこちらでご確認ください。
まず試験内容について以下にまとめてみました。
- 一次試験
<多肢選択方式試験>
・出題形式→マークシート方式(100問)
・試験時間→2時間30分
・内容→臨床心理士の業務内容に関する基礎的・基本的な専門知識や臨床心理士が知っておくべき法律の知識や仕事への姿勢について
<論文記述試験>
・出題形式→決められた時数の範囲内で解答
・試験時間→1時間30分
・内容→心理臨床に関するテーマについて1,001~1,200字以内の範囲内で論述記載
- 二次試験
<面接>
2人の面接官による口述面接試験。知識や技術の取得度の確認と臨床心理士としての基本的な姿勢や態度、専門家として最低限備えておくべき人間関係能力の実際が問われる
一次試験の合格者のみ二次試験に進むことができ、最終的な合格は「多肢選択方式試験」「論文記述試験」「面接試験」の3つの結果を総合的に判断して決定されますが合格基準に関しては非公開となっています。
資格審査の受験料は申請書類の費用(1500円)・資格審査の受験料(30000円)・合格後の登録料(50000円)の3種類の費用が必要となり、合計で81500円かかってしまいます。
臨床心理士試験の難易度と合格率
続いて難易度と合格率について見ていきましょう。
難易度
臨床心理士の試験は幅広い知識と経験が必要なものの難易度はそれほど高くないと言われています。
一次試験は暗記でカバーできる専門知識よりも実践においての知識が身についているかが問われるため単に知識や技術を学ぶだけでなく、学んだことと実習での経験を照らし合わせながら学びを生かしていくことがポイントとなります。2次試験の面接では今まで学んだ知識や経験、臨床心理士の資格を取る理由や将来像などが問われます。日頃から臨床実践で備えをしておくことが大切でしょう。
難易度が高くないとはいえ専門性の高い試験となるため、確実に準備をしておかなければ合格は難しいです。大学や大学院での学習以外にも予備校に通って試験対策をする人もいます。
合格率
近年の合格率を以下の表にまとめてみました。
| 年度 | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) |
| 2018年 | 2,214 | 1,408 | 63.6 |
| 2019年 | 2,133 | 1,337 | 62.7 |
| 2020年 | 1,789 | 1,148 | 64.2 |
| 2021年 | 1,804 | 1,179 | 65.4 |
表を見ると合格率は平均的に60%前後ですね。低くはない数字のため簡単なように感じるかもしれませんが合格率が高い理由として厳しい受験資格をクリアし、専門的知識がある人だけが受験できるという背景があります。決して簡単とは言えないでしょう。
臨床心理士試験に向いている人

それぞれ仕事には「適正」というものがありますよね。臨床心理士はどのような人が向いているのでしょうか。以下にまとめてみました。
- コミュニケーション能力が高い
- 精神力が強い
- 向上心がある
それぞれ解説していきます。
コミュニケーション能力が高い
クライエントとのカウンセリングで場の空気を読み取って会話ができる人は臨床心理士に向いているといえます。クライエントが相談内容をすべて本音で話してくれるとは限りません。話しやすい雰囲気を作り、本音を引き出す高いコミュニケーション能力が求められます。
精神力が強い
臨床心理士のもとには様々悩みや問題を抱えた人がたくさん訪れます。ときには重く難しい相談に出会うこともあるでしょう。そういったときには感情移入してしまい、自分の感情が揺れ動いてしまうと仕事に支障が出てきてしまいます。自分の感情をしっかり抑えて冷静な対応ができる精神力が必要といえます。
向上心がある
臨床心理士はクライエントそれぞれ価値観と向き合い、さまざまなケースと向き合うお仕事です。どんなケースにも対応できるように知識と経験が必要となります。また日々進化する臨床心理学を知るために日々勉強しなければなりません。研修や学会に積極的に参加しながら常に新たな知識を取り入れようとする姿勢が何よりも大切です。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
臨床心理士はクライエントの人生に関わりかつ良い方向に導ける、やりがいのある職業です。
うつ病など精神疾患が社会問題になっている昨今、的確なメンタルヘルスへの意識がますます強まっています。臨床心理士のような専門家のサポートを必要としている企業は増えており、活躍の場も増えていくでしょう。取得しておいて損のない資格のひとつです。